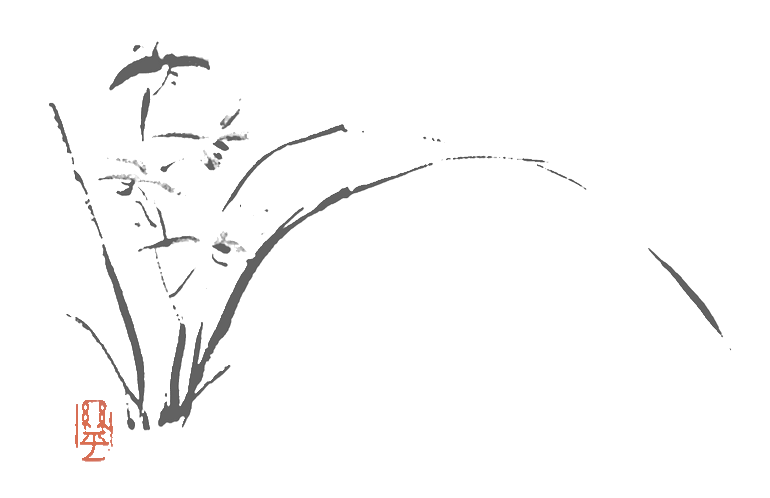渋谷博さんの思い出
岩本孝之
長らく本会の会長を務められた渋谷博氏が、昨秋ご逝去されました。蘭会でお世話になった一人として、心から哀悼の意を表しますとともに、思い出をいくつか述べさせていただきます。以下、少々勝手なもの言いになりますが、ご容赦ください。
私にとって、渋谷さんは関西寒蘭会そのものです。渋谷さんがいない会は、主人にいない空屋のような気がしています。渋谷さんと初めて出会ったのは、私が蘭を始めて間もなくの頃、昭和六十二年でした。関西寒蘭会で四国の寿楽園に行くことになり、そこで初めて話をしました。当時は豊雪が人気で、私もほしいと思っていました。渋谷さんが「うちにあるで」というので、後日神戸市ひよどり台の官舎にお邪魔しました。狭いベランダに蘭舎を置いて、きちんと並べてありました。新芽付きの一本立ちを分けていただき、興奮して帰ったのを思い出します。奥様もとてもいい方で、食事をごちそうになったりしました。私は当時職場の悩み事が多く、蘭が救いでした。週末になると、渋谷宅にお邪魔して、御神錦や司の華、大泉、渋谷さんが命名した月の童などを分けていただきました。今も我が温室にあります。その頃は寒蘭はとても高価で、花の咲くような木は手が届きません。渋谷さんは根っからの蘭好き、蘭の申し子のような人で、お金に糸目を付けず、好きな花なら四国でも九州でも出掛けて行って、「これが本物だ」と自慢していました。名前だけでなく、系統を調べ、原作者(最初の命名者)を尋ねたりしていました。
蘭作りは土作りから肥料作りまで、人まねできないほど、徹底していました。独特の発酵肥料作りを教えてやるというので、会の者が何人かお宅へ行って、蟹の甲羅をつぶしたり、藁を刻んだり、一日がんばって持ち帰りました。しかし後でうまくいい肥料ができたとは聞かないので、やはりこれは渋谷氏ならではのものだったのでしょう。鉢を空けると、根傷みなく真っ白、花はもちろん葉の一本一本の流れまで、気を配っていました。関西寒蘭会の優勝の常連でした。それもうべなるかなです。外側だけでなく、家の中の一室を蘭の部屋にして、高級品を育てていました。「蘭に悪いから早く寝ようね」と夫婦で話していたとか。奥さんもよくできたものです。 私は会に入って十年以上入賞すらできませんでした。渋谷名人から見れば、よほどできの悪い弟子だったと思います。それでもぼつぼつコツがわかるようになり、入賞、優勝が増えていきました。うちの蘭舎を見た会員が、「渋谷さんとおんなじようにしているなあ」と言ってました。
渋谷さんが新宮の家に移ってからも、よくお邪魔しました。奥さんといっしょにご馳走に連れて行っていただきました。我が家にもご夫婦で来てくださり、近所の蓮御堂(蓮池の下に寺のお堂がある)へ案内したりしました。私がぜんべえの里という里山公園を作った時も、来ていただきました。
その奥さんがまもなく急死して、ショックであったと思います(病気が重かった奥様に、私は花を送りました。無理をして奥さんが電話に出て、苦しそうな声でお礼を言ってくださいました。その言葉にならない声が今でも耳に残っています)。
渋谷さんはしかし一人で生活して、元気を取り戻したように見えました。お宅は清潔で、台所も冷蔵庫の中もきちんと整頓されていて、性格・人柄がうかがえました。蘭作りと同じです。私も妻が病気でほとんど一人暮らしでした。渋谷さんに男のひとり暮らしの知恵を教わりました。
一方で、人の面倒見がよく、快活で磊落なところがありました。私の淡路の家にもよく来てくれましたが、そのたび女性を連れていて、来るたびに違うので、どうやって知り合っているのだろうと、うらやましくさえ思いました。彼は刑務官で、その仕事の関係もあってか、カウンセリングができたのだと思います。女性の悩み、相談にも親身に対応していたのでしょう。「こんなことでもなかったら(ひとりで)生きていけんよ」と笑っていました。
蘭を愛し、人を愛し、人の心に思いを残して逝った渋谷さん。世間並みの出世もできたのに、断って蘭にかけた一途な人生。思い通りに生きた立派な人生であったと思います。きっとあの世でも、マイペースで楽しくやっていそうです。不肖な弟子ですが、またお目にかかりたいです。ありがとうございました。
心からご冥福をお祈りいたします。
Back to top