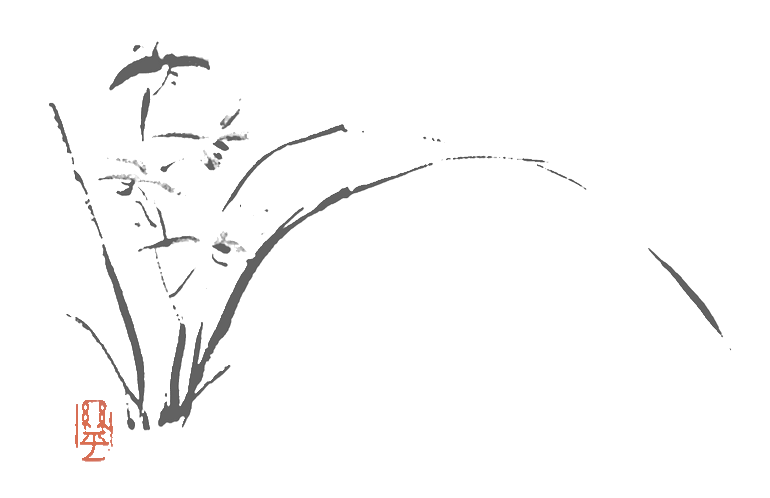- About
- News
-
Gallery
関西寒蘭会-menu - 素心53号 Digest
- 素心52号 Digest
- 素心51号 Digest
- 素心50号 Digest
- 素心49号 Digest
- 素心48号 Digest
- 素心47号 Digest
- 素心46号 Digest
- 素心45号 Digest
- 素心44号 Digest
- 素心43号 Digest
- 素心42号 Digest
- 素心41号 Digest
- 素心40号 Digest
- 素心39号 Digest
- 素心38号 Digest
- 素心37号 Digest
- 素心36号 Digest
- 素心35号 Digest
- 素心34号 Digest
- 素心33号 Digest
- 素心32号 Digest
- 素心31号 Digest
- 素心30号 Digest
- 寒蘭の造形美
- 東洋蘭用語集
- 会員BBS
- Forms
- Members
日向(ひむか)の国訪問
山内 敦入
日向の国。東は洋々と青海原が開け、神武東征の神話を産み、背後に霊峰霧島がそびえ、並び立つ峰々のうち、高千穂の峰は天孫降臨の地。西都原の古墳群、神話伝説に彩られたロマンの国。近代に至りこよなく酒と旅を愛したロマンチスト若山牧水を産んでおります。
光に満ち溢れた日向の国に寒蘭が生い育ち、寒蘭にロマンを求めた蘭入達の夢は大きく日向の蘭を全国に広めるとともに、全国の銘品を集め質量共に日本一の花会を開催されています。
寒蘭の自生地の蘭人達はお国目慢が強く、自国の花に強くこだわり、他国の花を軽視する傾向があるなかで、自国の花に深い愛情を注ぐと共に、全国の花に自国の花同様の愛情を注がれる日向の国の蘭入のロマンは壮大といわねばなりません。
十一月十六日・十七日、日向寒蘭宮崎県大会を訪ね、名人として全国に聞えた栗原稔さん・金丸良敏さんのお棚を拝見しました。栗原さんのお棚を拝見してまず気付いたことは、蘭室の中央に蘭が置かれ、通路は窓側.壁側につけられ蘭の周りを廻るように配慮されていました。
光線・通風がなるべく均等化されるようにという工夫かと思われますが、通路を真中にとり、両側に蘭を置く、一般的な配置と異なり、名人の配慮は]味違うと感心したものです。棚には上々作の稀貴品が並び、見学者一同を羨ましがらせました。
栗原さんは稀貴品の殖し方について懇切丁寧に教えて下さいました。稀貴品を増殖したいのは蘭人の念願ですが、その方法を教えて下さる方は少ないものです。それを初対面の我々に全てを教えて下さるのには感激しました。
その日の夜は永年の馴染の藤崎さんのお世話で懇親会が開かれました。趣味を同じくする者同士は有難いもので十年の知己のように蘭談が弾み、楽しい有意義な一夜でした。
翌日、花会会場を訪れ、昼食時に金丸さんのお棚を拝見しました。広い庭の一角に蘭室があり、天井が高く天窓が設けられ、通気性に意を用いられた蘭室でした。日向の国の気候・風土と蘭室の場所を考えてのことと思われました。通気性に配慮されるとともに、地面より一段掘り下げられ、乾き過ぎぬように配慮されておりました。
棚には栗原さんと同様全国の銘品が並び、特に「チャボ」の稀貴品が数多く並んでいました。栗原さん・金丸さんのお棚を拝見して、環境を考慮され細心の注意を払って創意工夫をこらしておられるのが印象的でした。広いお庭で日向の国にふさわしくサンサンとふり注ぐ太陽のもとで、持参した弁当を開きました。金丸さん宅の臼家製の漬物を出して頂き、都会では仲々味わえない故郷の味に、一同舌鼓を打ちました。
食事をしながらの歓談中、話がたまたま「覆面パトカー」に及びました。その時、渋谷会長が「覆面チャボ」と口走り、一同、一瞬工ーという感じで沈黙。次いで爆笑の渦また渦。最近、渋谷会長はゾッコン「チャボ」に惚れ込まれ、稀貴品の拾集に熱中されています。会長の脳裏には、日夜「チャボ」が焼き付いていたのでしょう。その上、つい先刻まで金丸さんのお棚で稀貴品「チャボ」の数々を拝見し、頭は「チャボ」で満杯。「覆面パトカー」というところを、思わず「パトカー」が「チャボ」に化けたわげです。
渋谷会長は在職中、職場と自宅が至近距離だったので、仕事中に蘭のことが気に懸かると、仕事を中断し蘭を見に帰られた由。蘭に対する思い込み・情熱・愛情は並々ならぬものがあります。
「覆面チャボ」の件でふと思い付いたことがありました。それは、我が身の蘭に対する態度でした。私は蘭を入手する際に、何よりも花の美的価値と金銭的価値とのバランスを重視するのをモットーとしてきました。
私が蘭を始めた頃は西谷物の全盛期でした。私は、花の美的価値は認めても金銭的価値がベラボーに不釣合で、馬鹿々々しい気分になり、欲しいとは思いませんでした。寒蘭熱烈愛好者のヒンシュクを買うかも知れませんが、当時一千万と騒がれていた『豊雪』よりも、私の好みにもよりますが、一株数千円の中国春蘭『宗梅』の方が美的価値は上だと思っていたのですから……。
まあそれはそれとして、ふと思い付いたことというのは、どうも目分は蘭に惚れ込んでいないな……ということでした。渋谷会長のように、蘭に惚れ込んでいるのなら、ただ欲しいの一念で他のことは考えない、考えられない、というのが本当ではないかということでした。こう考えると、我が家の蘭が全く不出来な原因がわかってきました。蘭に惚れ込んでいない私の姿を見て蘭達は、「こんなオッサンに養われるようになったのは身の不運」と完全にソッポを向いているようです。
作でいえば『日光』のような作り易い木を性懲りもなく枯すこと三度。枯らした時は生あるもの生命を奪った自責の念に駆られますが、間もなく「生者必滅」は世の習。「ナムアミダブツ」でハイおしまい。あまり口惜しいとも残念とも思わず、どうしても欲しかったら、そのうち金を貯めて買やあいいや、といった調子。蘭に惚れ込んでいる人なら桔した無念さに夜も寝られないくらい悩み、反省し、さまざまな工夫をされ、道を開かれると思います。
花に関しても作同様、進歩が見られません。むしろ初心者の頃の方がまだましでした。三十年来、毎年毎年本花会(うちの会では早花・本花・晩花と三回開催)に出品していますが、一度として入賞の経験なし。ギネスブックに掲載されてもいいような珍記録の持主です。それでまあよく三十年間蘭が続けられたものだと驚かれるかも知れませんが、 一つの秘密があります。
私は年金生活に入るまで教師をしておりました。慣い陸となって、なにかというと講釈をしたがります。うちの会で私のことを「『手八丁口八丁』というが、アイツは口はそこそこ達者だが、手の方は一丁」というのが通り相場になっております。このことは自他共に認めるところでありまして、本人は「『作下手・咲かせ下手』で三十年以上蘭が続げられるのは、あることないことつきまぜて、講釈する楽しみがあるからよ」と平然とうそぶいております。
「覆面チャボ」から話が横にそれました。花会の会場、MRTミッワのダイヤモンドホールは天井の高い立派な大ホール。出展数三三八鉢。質量共に日本一の花会にふさわしい会場です。
総理大臣賞は、新花で時流にのっている青花大輪.ベタ舌風・弁色も濃く、花型は端正・弁の切れがよく、花間も豊かな良花でした。トップ賞授賞を機に『大吉』と命名されました。
会場には全国のトップクラスの銘品が綺羅星の如く並び、眼福を得ること間違いなしというところです。日向の銘花『日向の誉』『司の華』などは入賞花がそれぞれ七点ずつあり、上位の賞・下位の賞花を見比べられ、花を知る上で参考になりました。紅花の部で『華神』.『日向の誉』の部門が設けられていたのも、日向ならではの想いを強くしました。
審査部門が細分化されていたのも大きな特色でした。紅・更紗・青は無点・有点に分けられています。公平を期し、審査しやすくする合理的な方法だと思われます。
素心は素心と準素心。ベタ舌は青べ夕舌とその他のべ夕舌。小花の部。奇花の部。入工交配の部。チャボの部。葉チャボの部。柄物の部に分けられています。それぞれの部門に金銀銅の賞があります。部門別の細分化はまず何よりも出品数が揃わなげればなりません。出品数が揃うということは会員達の熱意の賜物です。部門別を細分化することは、出品者の熱意に応える極めて効果的な方法だと思われます。
会場で気がついたもう一つのことは、会場の中央に業者のコーナーがあったことです。 一般の花会会場では、正面雛壇に向っ.て会場の中央に何列かの飾棚があり、業者のコーナーは入口の壁際の辺りに置かれております。この場合、業者の売店は花会のお添え物的な印象を持つのは私の独断でしょうか……。
花会の中心はいうまでもなく花です。しかし、花会に出かける蘭人達は花を見る楽しみと共に蘭を買い、さまざまな蘭を見る楽しみも大きなものがあります。花を楽しみ蘭を買い、さまざまな蘭を見る楽しみ、一石三鳥の楽しみがあってこそ会は盛り上ると思います。
花会会場の片隅でなく中央に業者のコーナーがあることは、会場中央に人の波・渦ができることです。会場の片隅に入が集まるより、中央に人の集まりがある方が、会場の熱気を高めるのに効果的なことはいうまでもありますまい。会が盛大になればなる程、業者の協力なくして、一層の発展は期待できないでしょう。
日向寒蘭宮崎県大会を参観し、日向をはじめとする全国の銘花に酔うとともに、日本一の花会を運営される会長.役員会員の方々のさまざまな創意工夫・配慮に感じ入りました。我々にとって実に有意義な二日間でした。
末筆ながら、お世話になった児玉国光会長はじめ、役員・会員の皆様、なかんずくお棚を拝見し、いろいろご教示頂いた栗原稔さん・金丸良敬さんに厚く御礼申し上げます。今後ともよろしくご指導ご交誼の程、お願い致します。
我が家の蘭作り
渋谷 博
はじめに私が蘭を作りはじめてから、二十七年余りになりました。蘭との出会いは昭和五十三年神戸に転勤してからのこと、公務員宿舎の中での蘭作りが始まである。
その蘭作りについて「蘭舎のない蘭作り」〔素心・第十六号〕次いで「ベランダでの蘭作り」〔素心・第二十二号〕を掲載しました。
その後、定年退職を迎え、郷土で小さな蘭舎を設け、のんびりと蘭作りをはじめております。今度、はじめて蘭舎で蘭を作ることになり、蘭舎の様子や蘭作りの方法を紹介いたします。
一 蘭舎について
1 蘭舎A(二段窓タイプ)
自宅東側に縦列して二棟(寒蘭用・春蘭用)を設ける。蘭舎に沿って東側に小川、その東は空地で風通し陽光共によい。
その仕様
床 = 地下一メートル土砂を除き、バラスを入れ、排水をはかる。
遮光= 蘭舎周囲に、アーチパイプ(農園レーム用パイプ)を組立て、遮光ネットの止具はパッカを使用(図示1)加温= 温床線配備を施す。

2 屋内蘭室・簡易型蘭棚(テラス)
自宅二階、東側半分を蘭室として建設(図示
2)、南側テラスに簡易型蘭棚を設ける。
その仕様
天井= バスリム様式
周囲= ガラスサッシ戸
床 = タイル張り、排水孔を設け潅水可
能とする。
用途は、バック木、作落ちした木、小木等、
無加温の蘭舎で越冬困難と思われる蘭の養成、また、春蘭の開花室として、冬期間のみ使用している。
なお、テラスの蘭棚は、春期のみ山野草、エビネの作場に使用している。

3 蘭舎B(木製造り)
昨年三月、蘭舎Aの東側に家屋が建ち日照不足となり、急きょ蘭舎B(寒蘭用、春蘭用)を設ける。
その仕様
天井= 波板張り
床 = 四十糎土砂を除き、バラスを入れ排
水をはかる。
遮光= 天井波板四十糎上に、遮光ネット覆用の棚を設ける。
加温= 設備なし
当蘭舎は日当りよく、完備したはずの蘭舎Aよりも上作である。
4 蘭舎Aの用途
日照時間が少なくなったことで、年間を通しての蘭作りはよくない。
しかし、夏期は涼しく冬期は一層冷えるので、夏は作落ち木やバック木、冬は春蘭花物の休眠作場に使用している。
二 蘭作について
1 通気
梅雨明けから十月までは窓を取りはずし通風をよくする。冬期においても、昼間は窓を開放している。
2 遮光
遮光ネットは夏期用(シルバ)、冬期用(黒)を区別して使用している。
梅雨明けから夏用に、十一月から冬用に張り換えている。
なお、遮光ネット下に防虫ネットを年中通して設置している。
3 用土等
用土は全て自分で配合している。その用土の種類、粒大、配合比は次のとおり。
(1) 用土の種類(四種類)
鹿沼土、薩摩土、マルチ蘭土(焼赤玉)、ゼオライト
(2) 粒の分別(四種類)
大粒(親指大) 中粒(小指大) 小粒(大豆大) 極小粒(小豆大)
(3) 配合比
鹿沼土 1/3 焼赤玉土 1/3
薩摩土 1/3 ゼオライト 若干
(4) 用土の量比
成木=大粒 1/4 中粒 2/4 小粒 1/4
中木=大粒 1/5 中粒 3/5 小粒 1/5
小木・根痛み木=中、小、極小粒を適量
毎年、梅雨明け後と十一月に上砂を交換する。
(5) 作鉢
京楽焼鉢のほか、最近、中木や小木はプラ
鉢を使用しているが上作である。
4 植え替え
通常二年毎、時期は秋の彼岸後、花のある木
は花後に施す。
5 潅水
水道水をホースで直接施す。梅雨時など新木の成長期は早目に、冬期は遅目に施す。用土の酸性化否は、植え替えをよく行うことで心配していない。
6 使用している肥料
(1)活力剤
メネデール ネオグリン HB―101
(2)有機質剤
ミネハグリン(フラワード)
トップドレッシング(グリンキング)
自作肥料
(3)マグアンプK
肥料は基準量より薄目、潅水の翌日施す。成長期は窒素系肥料、成木には主にリン酸カリ肥料を施す。梅雨期は病気が発生しやすく、葉面散布は施さない。
なお、マグアンプKは植え替え時のみ、十五粒程度、上砂中に混合している。
7 消毒
盛夏時期の消毒で留意しておくことは、殺虫剤で花芽や新葉に障害を与える薬剤があり、散布には注意が必要である。
8 花期の管理
七月下旬頃から花芽が出はじめるが、色花の花芽は摘み取ることもある。まず、よい発色の花が咲かないこと。花芽の上に、土もりすることも一方策であるが・・・。
九月に出た花芽は良花が期待できる。それは渓谷の紅葉同様、昼夜の温度差が大きく、また、適当の湿度があるからと思われる。
とはいえ、単に昼間の温度を上げ、温度差をつければよいというものではない。
「山に上げる」(高地で開花させると発色がよい)とよく言われるのはその理由からである。
そこで色花の発色方法についてまず認識しておきたいことは、春蘭の花色の出し方同様、同じ紅花であっても、その花個々に色素の含有値が異なることから、採光の強弱によって発色の変化が見られることは明らかである。
従って、方策はその年の気象条件に始まり、作場内の採光状態、鉢の位置、等々を観察し、記録の積み重ねにより確立を追及する方法以外にないと思われる。
私個人の意見としては、その基礎知識を認識していることが必要であるが、あまり花色にこだわらず、のんびりと花作りをしたいものである。
その他、花軸の仕立て方や花配りについては素心第二十二号に記しているが、その仕立て方は人それぞれ好みがあり、今回は記述しないことにした。
おわりに
以上、我が家の蘭作りについて全てを記しましたが、この方法はあくまで私の作り方であって、決して良いというものではありません。
蘭の作り方は、基本である自然をベースに作者の作場に合った作り方をすることが必要ではないかと私は思っております。
自然観を求めて「屋久島の旅」
森江 潤二
寒蘭に自然観を感じ、自然観を探し求めていたこの三年ほど、屋久島を又屋久杉を観に行けば何か感じる事ができるかもしれないと、決行を決めたのが今年の初めだった。
いろいろ下調べする中、縄文杉まで日帰りで十時間はキツク、この老体二人では無理せず山小屋で一泊する事を基本にして屋久杉に会ってこようと決め、白谷雲水峡を始めとして、縄文杉まで行き、近くの高塚小屋で一泊。ヤクスギランド、千尋の滝等を主目的に四泊五日の島一周の計画を立てた。
七月十八日大阪南港から鹿児島志布志港まで船旅、志布志から桜島を眺めながら鹿児島へ鹿児島市内観光をして時間を過ごし、鹿児島で一泊、翌朝鹿児島港から屋久島へ、近づく屋久島は薩摩半島、大隈半島、種子島などとやはり違っていた。まだ梅雨明けはしておらず山は雲を抱いていたが、周囲百kmの小さい島ながら二千㍍に迫る山があるだけに雄雄しく見えた。昼過ぎに宮之浦港に着く。港をはじめ町並みは素朴で海岸沿いに点々と人家等が見えるが急峻な山並みが目立った。その日は宮之浦の町を、環境センター、屋久杉自然館等を見学。宮之浦の民宿で泊まる。翌朝白谷雲水峡登り口まで車で三十分、登山用具を調え、午前九時前に出発 登山口で名簿に記入、入山料を払い管理棟のおばさんにコースを聞かれ、縄文杉に四時頃着くでしょうと言われ安堵すると同時にゆっくり登れると思ったのでした。
しかし、登り始めると急登で初日から息絶え絶えになる。しかし屋久杉、苔むす大地に魅せられながら、屋久鹿にも励まされながら辻峠まで三時間ほど掛かった。まだ先は長いと思いながらも辻峠から三十分程の所に太鼓岩があり見晴らしが良いと屋久フェリー船上で教えてくれた人があり、そちらに向かう。太鼓岩では確かに見晴らしは良かったがガスがかかり山並みは見えなかった。ここで昼食を取る。
屋久島は半日歩いただけだが、水の島といえるだろう。白谷雲水峡も常に水の流れる音が聞こえていた。ここでも小さな滝のような音と流れが見える。太鼓岩を後にして辻峠を下ればトロッコ道まで少しの道のりと思っていたが約一時間掛かる。途中 道を間違えたかと思うばかり遠く感じた。案内地図ではほんの近くなのである。やっとトロッコ道に出たと言う思いと予定時間をオーバーしており、少し頑張らなければ、高塚小屋の到着に日が暮れるという焦りが出始めてきた。なだらかなトロッコ道で遅い女房の足を引っ張る積りで歩を早めた。道案内では大株歩道まで一時間、途中下山者に道を譲ったり、譲られたりしながらやはり川の流れを聞きながらの歩行が続き一時間を経過、しかし未だ着かない。道案内は健常者の足取りか、自分の老化が進んだ結果なのだろうかと恨めしく感じながらも一時間十分かかってしまう。ここで挽回するどころではなかった。一休みしてここからが正念場と自分に言い聞かせ、急登に立ち向かう。ウィルソン株まで三十分あまりここでも道案内時間を超過、このウィルソン株は切り株だけだが太閤秀吉が島津家に上納させた切り株だとある。株の中は畳十畳ほどの広さ、神体が祀ってあり参拝、湧水がある。水を戴きなお、夜食用の水として2リットルをペットボトルに詰める。到着時間を気にしながらウィルソン株を後にする。大王杉まで一時間あまり、いよいよバテてくる。夜食用の水2リットルの水が肩に食い込み、腰にも痛みを感じ出した。(この旅の前に腰を痛めていた)腰と肩が繋がっている事を痛感、肩はパンパンに張ってきた。百メートル歩くと休み五十メートル歩くと休み、息絶え絶えになる。下山客にも会わなくなり、もう縄文杉まで近いと女房に言いながら、一歩一歩前進という状況であった。そして、それらしき人工の階段がありやっとたどり着く。午後6時であった。縄文杉は矢張り大きかった。圧倒される。つい手を合わせる。先客が一人、百名山を目指している岡山の人で我々を追い越して行った人だった。お互い写真を取り合いその人は高塚小屋のスペースをとっておくと先行した。
女房と二人きりになり縄文杉を独占。コーヒーとウィスキーで乾杯を上げた。現在縄文杉には立ち入りが禁止されているが対象になる者がいなければ写真での縄文杉の大きさが分からないだろうと思い謝りながら縄文杉にタッチ。(写真)

高塚小屋では十人ほどが外で食事後の歓談に花が咲いているなか押しかけたが歓迎してくれる。先に陣取りをしてくれていた人に夜具の準備をすすめられる。山の日暮れは早く、夜食を済ませた七時過ぎには薄暗く、片付けもそこそこに寝袋の中に入る。締め切った非難小屋は蒸し暑く人のいびきもあり、寝付けなかったが何時の間にか寝てしまっていた。
翌日は良く晴れた(梅雨明けしていた)素晴らしい景色のなかコースを変えながらの下山となる。そしてその後ヤクスギランド、トローキの滝、千尋の滝、大川の滝、ガジュマル園など廻るが、平穏に過ぎた。雨にも遭わず、屋久島での四泊五日の旅は終わった。
屋久島は先にも言ったが水の循環の島だ。例を見ない島だと思う。黒潮の恩恵を受け、高い山と水、苔が織りなすハーモニーのように感じられた。高い山は黒潮から上がった水蒸気を冷やし、膨張し、霧となり雨となる。この循環が屋久杉を育てた。屋久島は花崗岩が競り上がって出来た岩盤の島である。島の人は雨の多い屋久島の水は蒸留水と言っている。したがって山の水には魚も住めないと言う。又島の山の水はどこでも飲めるのだそうである。こういう所だからこそ屋久杉が育つのだろう。栄養も少なく年輪が密で長生きでき、樹脂は木を腐らないようにしているのである。御承知のとおり屋久杉とは千年を超えた物をいいそれ以下は小杉と言っている。人口植林の杉は地杉である。又屋久杉は標高八百メートルから千六百㍍の比較的高地で生えている事も環境が適しているのであろう。ちなみに縄文杉の生えている場所は一三〇〇㍍ほどのところである。木の胸高周囲一六㍍あまり、直径五㍍あまり、高さ約二五㍍と比較的低い。これは高地で風などの影響の所為だろう。
この環境を変えないように人間は考えなければならない。登山道を見ても根が踏み荒されささくれた根は見るに絶えなかった。これからも大勢の人間が訪れるであろう。山小屋も避難小屋と言うことであるが、入山料を値上げしてでも、最小限環境を守る為の開発が必要だと思われた。これまで人間は山の恩恵を受けながら、損得勘定だけで山を見てきたように思われる。屋久島には分かりやすい自然そのものが残っている。これは国の財産である。いや地球の財産である。屋久島にも寒蘭があるのは知っているが目に付かなかった。寒蘭がありそうな西部林道沿いの山は屋久ザルが多く、車を止められなかった。というのも、ヤクスギランドからの帰り道屋久サルを見つけ近づいた瞬間車に飛び乗られ、三十分間ほど餌を出せと粘られた。このサルは相当経験を積んだサルのようだ。人間から餌を取れると知っていた。
横道にそれたが、ヤクスギランドは皇太子が視察にきたようだ。屋久杉を守るようによく整備されていた。愛子様にも、愛子岳、縄文杉に御行幸願わなければならないのか。
皆様もどうか感動を掘り起こしてもらいたい。自然観を感じた時ほんの少しの時間をその事に思いを馳せていただきたい。そこには必ず環境を守る何かの示唆があります。寒蘭を守り地球を守るのはこれしかないと思いますが如何でしょうか。屋久島の自然がこの後も永久に続く事を願い、つたない文を置く。
合掌 平成十五年八月十五日
「文人作り」に思う
野口 眞人
関西寒蘭会では、一昨年の展示会から「寒蘭文人作り」の試みが行われていますが、まだ漠として全体像が見えない状態が続いています。新たな試みが直ちに結果を出せるわけはなく、このような状態に有るのは当然だと思いますが、会員の中には「一体どこが文人作りなのか、ただの捨て作りではないのか…。」との疑問を持っている方も有るのではないかと思います。私が率先して具体例を示せれば一目瞭然かも知れませんが、残念ながらそれほどの力量も、完成した技術も持ち合わせていません。そこで、従来の仕立て方とどこが違うのか、どこを鑑賞するのかを考えて見たいと思います。当然ですがこれは私の私見であり、「文人作り」を目指している方々の、共通認識でも価値評価でも有りませんので、最初にお断りしておきます。最初に「自然観」に付いて少し触れておく必要が有りそうです。従来の仕立て方は、品評会に出品する事を主眼にしたもので、「立派である事」「鮮やかであること」「バランスが優れている事」を評価しているのに対して、文人作りでは「自然であること」「風情があること」「可笑しみ(他の花には無い独特の味わい)がある事」等が鑑賞の対象であると考えます。従って、従来の仕立てが「作品」を目指しているのに対して、文人作りは「自然の有様の表現」を目指していると考えても良いと思います。何よりもこの視座の違いを理解する必要があり、これが解らないと「ただの捨て作り」との差異が見えてきません。
解り易い例を引けば、チャボや奇花の鑑賞がそれに当たると思います。これらの花を「作品として」如何に努力しても、優勝はおろか入賞することも難しかったのが、従来の展示会の持つ品評会的性質なのです。この様な側面は、ベタ舌花や垂れ舌花の評価にも現われていました。これらの花は「端正」でも「鮮やか(花色に限った事では有りません)」でも無く、ただただ「異様」であり「下品」だったのです。
時代とは恐ろしいもので、何時の間にかその様な「異様で下品な花」を「優れて個性的な花」と評価する様になりましたが、よくよく考えてみればこれは矛盾です。「端正でも鮮やかでも無い花」を、どのように解釈すれば「端正で鮮やかな花より優れている」ということになるのでしょうか。この様な矛盾に蘭界の誰も答えていません。それなら、この様な花をまとめて「可笑しみのある花」という別のカテゴリーで評価する方が、よほどスッキリと腑に落ちるのではないでしょうか。
また、従来の「名品」というカテゴリーに属している花も、本当に「品評会の作品としての評価」しか無いのでしょうか。これが「花」ではなく「農作物」ならスッキリするのですが、農家でもない我々趣味者が品評会を行うのは、ある種の滑稽さを伴います。元来農作物に文化性は無要で、肉質が柔らかく立派で新鮮で糖度が高ければそれなりの価格で取引され、誰も「文化的では無い」とクレームを付けません。しかし、東洋蘭が農作物と同様の評価をされるなら、趣味者などというものは「農作物の品評会のために大金を叩く」単なる浪費家でしか有りません。逆説的に「文化性に拘っているからこそ趣味者なのだ」という事になります。
では「東洋蘭の文化性」とは何でしょうか。限られたページ数で深遠な事をいうつもりは有りませんが、「花を観る」「自然を観る」「自己を観る」という視点のどれが欠けても文化的とは言えないでしょう。文化とは「いとなみ」の別名です。「いとなみ」とは日々の暮らしとその中で思う事柄です。それぞれの生活の中で培われた有様と考え方です。また、それぞれが観る世界でもあります。言い換えればそれぞれの自然観です。もし、それが花の上に表現されたら、「東洋蘭をやっていて本当に良かった。」と心から言えるのではないでしょうか。
この様に考えてみると、「文人作り」がいかに奥深いものであるかが、おぼろげながら見えてきます。翻って、従来の「品評会作り」が、農作物の評価と本質的に変わりの無い、表面的で形而下的なものである事が分かります。少なくとも私は、その程度のものと死ぬまで付き合う気は有りません。かといって、「文人作り」が見えている訳でも有りませんが…。
さてさて、何とも厄介な「文人作り」ですが、だからこそ面白いとも考えられます。誰かが「菊は誰が咲かせても菊、さりとて蘭は…」と言いましたが、立派に咲かせるだけなら、蘭と菊に何ほどの違いが有るでしょうか。漫然と「品評会作り」を行いながら、菊を揶揄するのは傲慢と言うものです。菊作りを馬鹿する事が出来るでしょうか。
東洋には西洋には無い独自の価値観が有るのです。大きさや色やバランスを比較するだけの「品評会」から抜け出すには、何よりもまず蘭に関する先入観を払拭し「頭の中を空にする」事が肝要ではないでしょうか。そこから、それぞれ別の具体論が見えてきてこそ「文人作り」なのだと思います。
寒蘭の多様性 ― 一筋縄でいかない面白さ ―
山内 敦人
「舌の芸」・「舌点の芸」ここ十年来、寒蘭の「舌の芸」が注目されています。「べ夕舌」・「垂れ舌」・「チャボ」などに見られる「お多福舌」などがもてはやされています。
最初に「舌の芸」が注目されたのは「素舌」「全面無点系舌」でした。その後十年ばかり「舌の芸」に対する関心が薄れていました。
元来、東洋蘭鑑賞の元祖は中国で、日本でもほぼ中国の基準をお手本にしています。中国では「弁型」は言うに及ばず「舌の型」・「舌点の型」にまで目を配り鑑賞の対象としています。
日本では、中国春蘭愛好者の間では鑑賞の基準として尊重されましたが、寒蘭界は余り関心を持たなかったようです。「弁型」はいうに及ばず「舌の型」・「舌点の型」ー「舌の芸」「舌点の芸」は、東洋蘭の魅力のポイントと認識した中国人の美意識は見事という他ありません。
「素舌」「前面無点系」をとりあげた時点で、「素舌」前面無点系は「舌の芸」だという認識を明確にしていたら、「べ夕舌」・「垂れ舌」・「お多福舌」も「舌の芸」として関心を持ったのではないでしょうか。「素舌」「前面点系」が注目された頃は、西谷物を中心に中輪咲の寒蘭らしい寒蘭の全盛時代でしたから、調和のとれた「素舌」「前面無点系」が評価されたのでしょう。それはそれとして寒蘭界は「舌の芸」は鑑賞の一つのポイントだと捉える突込んだ観方ー事の本質を捉えるより普遍的に見ようとする観方1に欠けているようです。
「舌の芸」が鑑賞の一つのポイントと捉えれば、寒蘭は春蘭以上に[舌の芸」の多様性を持っており、「舌の芸」が花の味わいに与える影響は、春蘭より顕著なものがあり、寒蘭の美とは、多様性に富んだ面白さにみちみちていると捉えられると思います。
「舌点の芸」ー舌点の打ち方も最近注目され「ベタ舌」も打ち方の一つでありましょう。「ベタ舌」でなくても、「ベタ舌」に近い舌点の強いもの、逆に舌点の打ち方が少なくて特色を発揮しているものなど多様です。
今注目されているものは、言うならば個性的な点の一見それと捉えやすい打ち方をしているものですが、単に舌点だけに注目するのでなく、舌点の色・舌の大小・舌点の並び方との関係、更に弁型・弁色・舌の色・子房・花軸との綜合的な関係性に目をむけるべきだと思います。
このような観方から見れば、舌の点の打ち方が一見個性的でないものでも「舌点の芸」として捉えられると思います。
例をあげれば桃味の強い小点が型よく並び、舌の色が白味の強いもので、花型の良い桃更紗の花などは美的価値が高く、数も少ないものです。阿波吠喰大谷の『大寿』などは、舌点は平凡ですが、舌点の色と子房・花軸の色がほぼ同色・弁色も黄味が強く、潭然一体となっていい花です。舌点の色・子房花軸の色がぼぼ同色という青花は案外少ないものです。
寒蘭の魅力は「舌の芸」「舌点の芸」が一つのポイントになりますが決して全てではありません。「弁型」「弁色」更には子房の色・長さ・花軸との綜合的な関係性を見なければなりません。綜合的な関係性とは単なるバランスではなく、それぞれのものが相互にどんな関係性をもって花の魅力を醸し出しているかということです。
「匂うという言葉があります。現在は臭覚に訴えることだけを指しますが、古くは、相互に影響しあって相乗効果を産み全体像を美的に高める、という意味で使われていました。寒蘭の魅力、更に美しさは「匂う」ことにあると思います。それだけに多様で複雑な味わいをもつものだと思われます。
ついでながら、よくいわれている多芸品について触れておきます。多芸品は多様性の一つで尊重すべきものでしょう。一般的に芸が多ければ貴重視されますが、芸と芸とが匂い合ってこそ意味があるので、芸の多さだけなら希少価値はあっても美的価値があるとは思えません。
寒蘭の美についてわび・さび・幽玄などといわれます。いずれも見せかけの美でなぐ、熟視頑味しなければ見えてこない美です。にもかかわらず、寒蘭界では単にバランスの良いもの・印象度の強いものがもてはやされる傾向性が強いように思います。これでは、わび・さび・幽玄美は大型かつ華麗・豪華さに対する対極的な美に終ってしまうでしょう。寒蘭の持つ芸の多様性とは何かを問い、芸の多様性の相互関係性を捉え、「匂う」ことの意味を考えて見ることは、一興かも知れません。
典型と破格
私が蘭をはじめた三十年前は、寒蘭の美とは、細幹で葉上にすっきりと抜け、花間よく四方咲・子房は長からず短かからず、花軸に対しバランスの良い角度を持ち、葉姿との調和よく、花弁はすっきりと伸び、弁の切れのよいもので、一文字・平肩・三角咲。西谷物を中心とした中輪咲が清楚・端正・優美・気品に溢れた存在としてもてはやされ、寒蘭の美的価値はこれで決まりといった風潮がありました。
寒蘭の花型を見ると細く、長く、弁質の薄いのが特色です。この特色は他の東洋蘭と一味も二味も違っており、寒蘭の存在価値を高めています。特に、弁の切れ1弁元から弁先への流れーの良いものは魅力溢れた存在です。従って、前述した寒蘭の美的価値が生まれてくるわげです。
しかし、寒蘭界が盛況を呈し会場が大型化するなど動機はともかくも、大輪花が端正さと伸びやかな力動感を持って登場してくると、花にふさわしく花軸も太くなりました。その上「べ夕舌」・「垂れ舌」・「お多福舌」・「チャボ」が登場してきました。寒蘭の多様性を発見し、多様性故に、活況を呈して来ました。「垂れ舌」・「お多福舌」は、一般的な正統な「巻舌」に比べたらやや型変りで、きっちりと型よく巻いた「巻舌」に比べると端正さに欠けますが、寒蘭の舌はよく見ると、花弁に対しやや小振りのものが多くー咲き始めはともかく咲ききると細るものが多くー完壁なものが少ないものです。その上「舌の芸」・「舌点の芸」を顕在化させるのは、「垂れ舌」・「お多福舌」の方がふさわしいと思います。騒がれる資質は十分持っていると思われます。
「べ夕舌」・「チャボ」は、従来いわれていた寒蘭の美からいうと、破格の異端児といえるのではないでしょうか。「ベタ舌」のクドサ、「チャボ」のズングリムックリした寸詰りの舌足らずさ、いずれ清楚・端正・優美・気品とは全く異質です。特に「チャボ」は広弁・短弁型で、伸びは悪く花間は詰り気味。一部の好事家以外は省みなかったのは当然かも知れません。
時代の風潮というのは面白いもので、流行り出すとその勢は止め難く、昨今はかつての古典的な銘花達は影の薄い存在になりました。「ベタ舌」・「チャボ」の流行は単なる流行だけでなく、動機はともかくも寒蘭の美の多様性の発見という意味を持っているのです。
「べ夕舌」の持つクドサは、パンチの利いた強烈な存在感を持っています。そして優品はそのクドサを「妖艶」、時として「怪奇」・「特異」な美に昇華させています。「チャボ」についても寸詰り、舌足らずさはユーモラスな愛敬ー諧譫味・可憐さーを待っています。「チャボ」のような短弁・広弁・広舌花は、花軸が伸び葉上高く抜け、花間をとり、四方咲に咲いたら間伸びがし、鑑賞価値を損うでしょう。輪数の少ないものなどは、洋蘭風に同じ方向に向ける方がよい場合もあると思われます。
昨今「大輪花」・「べ夕舌」・「垂れ舌」・「お多福舌」・「チャボ」の美の発見は、単なる流行のそれでなく、寒蘭の多様な美の発見という意味を持っているのです。なかんずく、「ベタ舌」「チャボ」の美の発見は、破格異質の新しい美の発見という画期的な意義があると捉えなければなりません。流行は一時の現象です。流行の去るとともに、「ベタ舌」・「垂れ舌」・「お多福舌」・「チャボ」が忘れ去られるとしたら、寒蘭界とは物事の本質を見ようとしない存在だということになるでしょう。
「べ夕舌」・「チャボ」Fの異質の美の発見は、かつてこれで決まりと思われた「寒蘭の美」の絶対性の否定という意味を持っています。かつての「寒蘭の美」は細く長く薄い弁質の持つ寒蘭の花のもっとも寒蘭らしい典型的な美ーお手本になるような美1だったのです。
ただ面白い現象が見られます。影の薄くなった古典的な銘花ですが、各地の花会を見ると結構健闘し、上位の賞を果たしており、流行の最先端を行く「チャボ」は「チャボ」の部門を設けてやらないと入賞できないような状態です。古典的銘花の美が典型であることを端的に示している証拠だと思われます。
私個入の好みで言えば、中輪咲の古典的銘花こそ最も寒蘭らしい寒蘭だと、頑なに信じ込んでおり、「ベタ舌」・「チャボ」は余程の優品でなければ食指が動きません。私のような傾向を持たれる方も間々あるかと思いますが、「ベタ舌」・「チャボ」が寒蘭の美に対して与えた意義は、個入の好みとは全く別間題です。寒蘭の持つ多様性が末永く共存して行ってこそ、寒蘭界は活況を呈するものと思っております。
人工交配種
最近入工交配種のよい花が出始めました。賛否両論があるようですが、大勢として受け入れることになると思われます。よいものはよい、美しいものは美しいとして受入れたらよいと思います。ただ、交配種ということは明記すべきだと思います。
入工交配種の登場は一層寒蘭界の多様性を増すことになるでしょう。ただ、次の点は明確に押さえておくべきだと考えます。潔癖な入達は自然種に拘わり入工交配種に異を唱えますが、本来、東洋蘭は白]然のままの原種です。寒蘭も野生の原種の小型シンピジュウムです。洋蘭との決定的な違いは、入工的な交配が行われていないということにあります。
自然の野生種を目然種、原種として保全して行くことの意義は重大なものがあります。野生の原種には、その根底に人工交配種にはない凜とした強靱な野生の生命力が宿っています。野生の原種の持つ強靱な生命力が美的にどのように現われているかーこのことこそ東洋蘭の持つかげがえのない価値だと思います。
人工交配で花の普遍性ー丸型・色の濁りない澄明さーに向って改良に改良を重ねた洋蘭の美に対抗できる美だと考えます。
洋蘭の世界でも原種があり、改良に改良を重ねた交配種の対極の存在として尊重されています。原種に対する尊重の念は入間の故郷を想う念と同様に、普遍的なものかも知れません。
寒蘭の人工交配を行うことは一足洋蘭の域に踏み込むことになります。ただ、このことの是非を間うよりも、事の本質をしっかり押えておき、原種を臼然のまま保全することの意義をわきまえ、交配種と原種の美的な差異をしっかりと認識することだと思います。寒蘭の場合は仲々判別しにくいとは思いますが、感性・美意識を磨くことに心掛けるべきでしょう。
今、「えびね」の世界は交配種の全盛時代です。神戸国際蘭展で「えびね」の交配種と原種を見比べて、東洋蘭の愛好者の多くは、交配種よりも原種の方に親近感を抱いていました。仲々面白い現象です。
ここでも物事の本質を間うことの重大な意義が間われているように思います。交配種が見事だからといって、原種の寒蘭は単なる交配用の種木視してしまうようでは、寒蘭界の見識の無さを露呈することになるでしょう。また反面、頑固に交配種を排斥することも視野の狭さを物語ることになるでしょう。
聞く所によると、寒蘭の遺伝因子を測定すると幅が広すぎて、寒蘭の遺伝子の典型はこれだという同定ができないそうです。ということは、白然の中で交配が行われているということではないでしょうか。寒蘭の多様性の秘密の一つはこんな所にあるのかも知れません。
寒蘭の持つ一筋縄で行かぬ面白さは、大いに生かされるべきだと思います。入工交配種の問題と本質をしっかり押えた上で、より寒蘭界を豊かにするために、肯定的に捉えた方が良いと思われます。