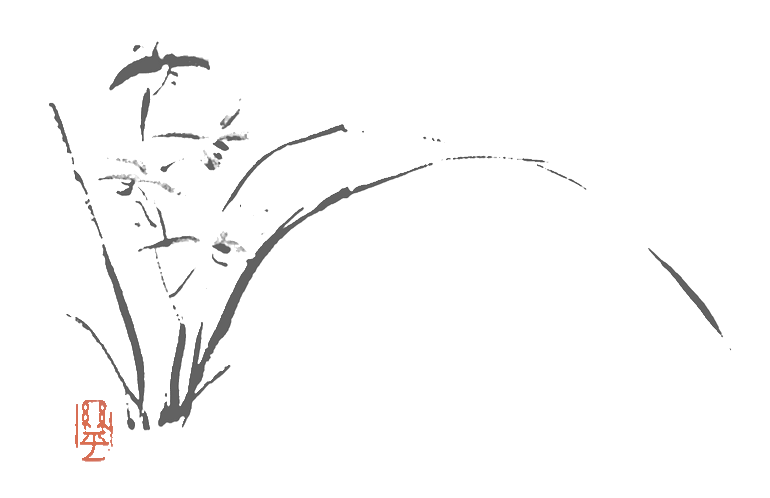意外と知らない農薬の話
渡辺 交
農薬は特に気にせず使っている人もいるかと思いますが、それぞれに特徴があり、それを頭に入れた上で使うとより効果的です。今回は語られることが少ない個々の農薬について解説してみました。農薬の種類によって粉だったり、液体だったりしますのでその解説から始めたいと思います。
○水和剤
水に溶かして使う粉状の薬のことです。水に溶けずにダマとなって残る場合があるので、良くかき混ぜて使いましょう。展着剤を入れると葉になじみやすくなり、薬の効果が高まります。水をはじきやすい植物には展着剤を多めに入れます。
○乳剤
石油のにおいがする淡褐色の透明な液体で、水に入れると乳白色になることから乳剤と呼ばれます。乳剤はそれ自体が展着剤の役割を果たすので、新たに展着剤を加える必要はありません。
○フロアブル
元は水和剤なのですが、水に溶けやすいよう液状にしたものです。白いどろっとした液体なのが特徴です。長く保管していると液が分離しますので、良く振ってから使いましょう。
○粒剤、粉剤
植物の根元に直接まいたり、土に混ぜて使う農薬です。このタイプの農薬は浸透移行性という性質を持ち、根から吸収されて植物の隅々まで行き渡るので奥に隠れた害虫にも効果があります。
次にランの栽培によく使われる殺虫剤を解説します。
○キンチョール
園芸用と言うより家庭用殺虫剤の代表格です。有効成分はピレスロイド。除虫菊に含まれている殺虫成分で、蚊取り線香に含まれているのもこれです。きわめて速効性で殺虫力に優れ、しかも哺乳動物に対してほぼ無害という殺虫剤の優等生です。「虫コナーズ」のように吊すと虫がよってこないタイプの商品にもピレスロイドが使われています。
キンチョールは手軽なのですが、スプレー式は噴射時に低温になるという特徴があります。これはスプレーの宿命なのですが、植物が凍傷を起こすレベルの低温なので、使う際は植物から離して噴霧しましょう。吊すタイプは棚場に吊しておくと防虫効果が期待できます。棚場に蚊が多くて困っている方にもオススメです。
○スプラサイド乳剤
カイガラムシの農薬ではカルホスと並んでよく使われる農薬です。有効成分はDMTP(メチダチオン)という有機リン系殺虫剤で浸透性があり、チョウやガ、コナジラミ、カイガラムシ、アザミウマ、カメムシなど幅広い害虫に有効です。効果の持続時間は長めですが、カイガラムシに対しては幼虫期(五~六月と八~九月)に散布するのが最も効果的です。
劇物に指定されているので、購入には身分証明書と印鑑が必要です。500ml瓶しか販売されていないので、個人で使うには少々もてあましてしまいます。
○カルホス乳剤
カイガラムシには前述のスプラサイドと同じくらいよく使われる農薬で、有機リン系に属します。有効成分はイソキサチオンで、チョウ・ガ、カイガラムシ、甲虫類など幅広い害虫に有効です。効果の持続時間は長めですが、浸透性が無いのでムラ無く散布する必要があります。カイガラムシ防除には幼虫期に散布するのが効果的です。土壌中では最終的に炭酸ガスに分解されるので土壌汚染を起こしません。温血動物では速やかに体外に排出されるので、人体への毒性は低レベルです。
これも劇物指定なので、購入には身分証明書と印鑑が必要です。カルホスは100ml瓶があります。
○スミチオン乳剤
四十年以上前に開発され、今でも殺虫剤の定番として使われるロングセラーです。有効成分はMEP(フェニトロチオン)。幅広い害虫に有効で、しかも植物の中深くまで到達するので、植物中に潜り込んだ害虫にも有効です。
○オルトラン水和剤
野菜の農薬として広く使われています。浸透性のため、内部に侵入した害虫にも効果があり、長い時間効果を発揮します。成分名はアセフェートで有機リン系に属します。水和剤と粒剤が販売されていて、粒剤は寒蘭のハモグリバエ予防に有効です。五号鉢一鉢あたり2gを用土表面にまきます。
○マシン油乳剤
名前のとおり機械油で、希釈倍率が百倍と濃いのが特徴です。気門を塞いで虫を窒息死させるためあらゆる昆虫に効果があるですが、植物の気孔も塞いでしまうため休眠期に散布するのが鉄則です。ホームセンターで売っているカイガラムシ用のスプレーはこれが主成分です。
○コテツフロアブル
成分はクロルフェナピルで、劇物に指定されています。ダニに対し非常に高い効果を発揮しますが、難点は価格が高いことと劇物指定であることです。100mlの小瓶でも二千円以上します。ハダニに悩まされている場合は置き場が乾燥しすぎている証拠ですので、これに頼るよりも環境を改善した方が良いでしょう。サビダニに対しては現時点で最も効果の高い薬です。
殺菌剤
○ダコニール1000
三十年以上前に開発され広く使われているにもかかわらず、未だに耐性菌が出ていない殺菌剤のエースです。有効成分はTPN(クロロタロニル)で効果は長期間持続し、薬害もほとんどありません。株分けの傷口に原液を塗ることもあります。耐性菌が出ないことから連続して使っても大丈夫ですが、予防剤なので病気の治療効果はありません。
○ベンレート水和剤
灰色カビの特効薬として広く使われましたが、耐性菌が出現しかつてほど効果はなくなりました。有効成分はベノミルで幅広い菌に有効、かつ浸透効果もあることから治療効果もあります。他の薬剤と混合したものもあり、チウラムを混ぜた「ベンレートT」、ダコニールと混ぜた「ダコレート」などがあります。
○トップジンM水和剤
ベンレートと並び、よく使われる殺菌剤です。有効成分はチオファネートメチルで、ベンレートと同じく幅広い菌に有効、浸透効果があり治療剤として使われます。実はベノミルとチオファネートメチルは兄弟みたいなもので、どちらも植物体内でカルベンダゾールという物質に変化し、これが殺菌作用の正体であることが明らかにされています。したがって、ベンレートが効かなかったからトップジンMを使う、というのは全く意味の無いことになります。
○銅水和剤
銅はそれ自体が殺菌力を持つ上に、植物の組織を丈夫にする作用があり、一石二鳥の効果があります。細菌病とカビの両方に効果があるのも特徴です。銅水和剤には無機銅と有機銅の二タイプが存在し、両方ともカビと細菌に効くのですが、無機銅は細菌病の方に強く、有機銅はカビの方に強いという特徴があります。植物の病気の九割がカビによるものと言われていますが、近年は細菌による病気も無視できなくなりました。カビと細菌の両方に効く銅水和剤は今の状況にうってつけの存在です。
しかし、銅水和剤は薬害が強いという弱点を抱えています。効き目は無機銅が強く、有機銅はやや劣りますが、薬害の強さも同じ順になります。私はサンボルドー水和剤(無機銅タイプ)を六月に五百倍希釈で散布したところ薬害が発生しました。春蘭では古木の葉が落葉し、セッコクでは新葉が茶色く枯れました。銅水和剤の薬害防止には炭酸カルシウムの添加が効果的なのですが、ランは葉が厚いから入れなくても大丈夫だろうと高をくくっていたのが失敗の元でした。ランには安全性が確認されているキノンドー(有機銅タイプ)をお薦めします。
農薬に使う水について
農薬散布に使う水は水道水を使うと思いますが、水がアルカリ性だと農薬の効果が弱くなります。水道水のpHの基準は五.八~八.六と定められていますが、八を越えるのはかなり高い部類で、植物の生育に影響が出ることもあります(ランは弱酸性を好みます)。水道水のpHの平均は七.五で、弱アルカリ性となっています。薬が効かないのは害虫が強くなっているだけではなく、水がアルカリ性だからという可能性も頭に入れておいてください。
Back to top